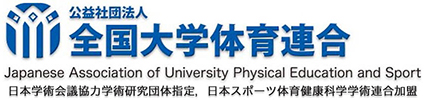会長ご挨拶
会長 長谷山彰国立大学法人北海道国立大学機構理事長、前慶應義塾長、前日本私立大学連盟会長、全日本大学野球連盟会長
 このたび安西祐一郎前会長の後を承けて、全国大学体育連合の会長に就任致しました。
安西前会長は当連合が創立60周年を迎える時期に会長に就任され、2022年の創立70周年に至るまでの長きにわたって当連合の発展のために尽力されました。この3年間は新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されていましたが、2023年3月22日、3年ぶりに対面で通常総会を開催し、遅ればせながら新旧会長が参加して創立70周年の記念祝賀会も催すことができて幸いでした。
創立70周年を迎え、大学体育連合は過去の歴史を振り返り、進むべき方向を模索する時期にあります。1949年の新制大学発足とともに体育は教育課程に組み入れられ、1952年、大学体育連合の前身組織である大学体育協議会が発足。1956年には大学設置基準で保健体育の最低必須基準が4単位と定められました。しかし、1960年代、保健体育を単位制度から外すことが提言されると、1970年代以降、大学改革論の中で必修見直しの考えが強まり、1991年の大学設置基準大綱化を契機に保健体育を卒業要件からはずす流れが全国の大学で一気に加速しました。
それに対して、大学体育教育協議会から大学体育連合への名称変更、社団法人設立認可を経て、2012年、ちょうど創立60周年を迎える年に公益社団法人の認定を受けるなど組織の改編を重ねながら、大学体育連合は大学体育教育の伝統を守るべく努力を続けてきました。その間、大学体育指導者養成研修会の定常化など研修事業や表彰制度の充実、また大学体育教育の実態に関する調査研究に加え、研究論文誌「大学体育スポーツ学研究」の刊行、「研究フォーラム」の開催などの成果によって、2019年、日本学術会議協力学術研究団体の指定を受けました。さらにはIT化の時代に対応した情報発信や広報活動の充実、日本プロゴルフ協会など外部団体との連携を強化し、体育・スポーツの振興にも活動の場を広げています。
大学が少数のエリートの学ぶ場であった時代から、大学進学率の上昇によってユニバーサル化の段階に移行し、社会と連携しながら多様な教育によって多様な人材を育成することを要求されている現在、大学体育も変化への対応を求められています。大学教育における正課としての体育と課外活動としてのスポーツとの関係、地域社会に広がるスポーツ活動、スポーツ庁の設立など国レベルでのスポーツ振興政策との関係など検討すべき課題はさまざまですが、めざすところは「大学をはじめとする高等教育機関における体育に関する研究調査を行い、成果の普及活用、相互の連絡、協力体制の確立、もって大学をはじめとする高等教育の発展に寄与する」(公益社団法人全国大学体育連合定款より)ことであり、この原点を踏まえながら前進しなければなりません。
「人生100年時代」といわれ、健康長寿社会を目指す動きが加速する反面、高齢者の加齢による筋肉量の低下、若者の体力低下が問題になっています。健康で長生きするためには一生を通じてスポーツに親しみ体力の増強維持に取り組む必要がありますが、それには若い時に専門性に裏付けられた正しい指導を受け、理論と実践の両面から合理的な運動法を身に着けることが大切であり、大学体育の役割は重要です。また研究教育の成果を社会に普及させることは社会貢献を目的とする公益法人の使命であり、2011年に制定されたスポーツ基本法の目指すところとも一致しています。
会長として、微力ではありますが、副会長、専務理事をはじめ理事会の皆様、会員の皆様、そして事務局の皆様に支えていただきながら、全国大学体育連合の発展のために力を尽くす所存です。皆様の変わりないご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
このたび安西祐一郎前会長の後を承けて、全国大学体育連合の会長に就任致しました。
安西前会長は当連合が創立60周年を迎える時期に会長に就任され、2022年の創立70周年に至るまでの長きにわたって当連合の発展のために尽力されました。この3年間は新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されていましたが、2023年3月22日、3年ぶりに対面で通常総会を開催し、遅ればせながら新旧会長が参加して創立70周年の記念祝賀会も催すことができて幸いでした。
創立70周年を迎え、大学体育連合は過去の歴史を振り返り、進むべき方向を模索する時期にあります。1949年の新制大学発足とともに体育は教育課程に組み入れられ、1952年、大学体育連合の前身組織である大学体育協議会が発足。1956年には大学設置基準で保健体育の最低必須基準が4単位と定められました。しかし、1960年代、保健体育を単位制度から外すことが提言されると、1970年代以降、大学改革論の中で必修見直しの考えが強まり、1991年の大学設置基準大綱化を契機に保健体育を卒業要件からはずす流れが全国の大学で一気に加速しました。
それに対して、大学体育教育協議会から大学体育連合への名称変更、社団法人設立認可を経て、2012年、ちょうど創立60周年を迎える年に公益社団法人の認定を受けるなど組織の改編を重ねながら、大学体育連合は大学体育教育の伝統を守るべく努力を続けてきました。その間、大学体育指導者養成研修会の定常化など研修事業や表彰制度の充実、また大学体育教育の実態に関する調査研究に加え、研究論文誌「大学体育スポーツ学研究」の刊行、「研究フォーラム」の開催などの成果によって、2019年、日本学術会議協力学術研究団体の指定を受けました。さらにはIT化の時代に対応した情報発信や広報活動の充実、日本プロゴルフ協会など外部団体との連携を強化し、体育・スポーツの振興にも活動の場を広げています。
大学が少数のエリートの学ぶ場であった時代から、大学進学率の上昇によってユニバーサル化の段階に移行し、社会と連携しながら多様な教育によって多様な人材を育成することを要求されている現在、大学体育も変化への対応を求められています。大学教育における正課としての体育と課外活動としてのスポーツとの関係、地域社会に広がるスポーツ活動、スポーツ庁の設立など国レベルでのスポーツ振興政策との関係など検討すべき課題はさまざまですが、めざすところは「大学をはじめとする高等教育機関における体育に関する研究調査を行い、成果の普及活用、相互の連絡、協力体制の確立、もって大学をはじめとする高等教育の発展に寄与する」(公益社団法人全国大学体育連合定款より)ことであり、この原点を踏まえながら前進しなければなりません。
「人生100年時代」といわれ、健康長寿社会を目指す動きが加速する反面、高齢者の加齢による筋肉量の低下、若者の体力低下が問題になっています。健康で長生きするためには一生を通じてスポーツに親しみ体力の増強維持に取り組む必要がありますが、それには若い時に専門性に裏付けられた正しい指導を受け、理論と実践の両面から合理的な運動法を身に着けることが大切であり、大学体育の役割は重要です。また研究教育の成果を社会に普及させることは社会貢献を目的とする公益法人の使命であり、2011年に制定されたスポーツ基本法の目指すところとも一致しています。
会長として、微力ではありますが、副会長、専務理事をはじめ理事会の皆様、会員の皆様、そして事務局の皆様に支えていただきながら、全国大学体育連合の発展のために力を尽くす所存です。皆様の変わりないご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
専務理事ご挨拶
「大体連とは、学生の身体教育にプロ意識を持った教員のネットワーク」
専務理事 村山光義 慶應義塾大学体育研究所・教授
2025年度より、葛西順一前専務理事よりバトンを引き継ぎ、全国大学体育連合の専務理事を拝命いたしました。微力ながら大体連活動の推進に取り組んでまいります。大体連は「大学体育」の充実によって大学・高等教育の発展に寄与することを目的としています。ここで、「大学体育」とは、正課の保健体育関連科目を大軸として、健やかなキャンパスライフを構築し、課外活動としての学生スポーツも支える身体教育の実践と言えます。それは、大学内で多くの学生を対象とした教育機会を持ち、人間形成の基礎教育として積み重ねられてきたものです。大体連はこの必要性を「大学保健体育基本構想」「体育系学術団体からの提言 2010:21世紀の高等教育と保健体育・スポーツ」などを通じて発信してきました。そして、大学体育教員の指導法・FD研修と養成講習、大学体育に関わる学術研究の推進・助成、社会との連携といった取り組みを続けてきております。
慶應義塾大学体育研究所・教授
2025年度より、葛西順一前専務理事よりバトンを引き継ぎ、全国大学体育連合の専務理事を拝命いたしました。微力ながら大体連活動の推進に取り組んでまいります。大体連は「大学体育」の充実によって大学・高等教育の発展に寄与することを目的としています。ここで、「大学体育」とは、正課の保健体育関連科目を大軸として、健やかなキャンパスライフを構築し、課外活動としての学生スポーツも支える身体教育の実践と言えます。それは、大学内で多くの学生を対象とした教育機会を持ち、人間形成の基礎教育として積み重ねられてきたものです。大体連はこの必要性を「大学保健体育基本構想」「体育系学術団体からの提言 2010:21世紀の高等教育と保健体育・スポーツ」などを通じて発信してきました。そして、大学体育教員の指導法・FD研修と養成講習、大学体育に関わる学術研究の推進・助成、社会との連携といった取り組みを続けてきております。また、大体連は大学が会員となっていますが、大学体育の価値を実践し、改善に努力してきたのは、現場の各教員の皆さんです。「体育」という言葉や内容が「スポーツ」に置き換えられ、集約されて来ていますが、「知育・徳育・体育」という三育が人間教育の重要な要素であることには変わりはなく、身体教育の重要性を認識している多くの教員の力によって我が国の大学体育は維持されて来ています。従って、私は、大体連とはこうした「学生の身体教育にプロ意識を持った教員」のネットワークであると考えています。
現在、大学は、少子化、財政難、国際競争力の低下といった危機に直面しております。この競争的現状に立ち向かうべく、各大学は独自に3つのポリシー(アドミッション・カリキュラム・ディプロマ)を掲げ、教学マネジメントの推進によってポリシーの実現を進め、人材の輩出に努力しています。また、社会は共生や持続性の価値を求め、人々の生活における「Well-being」が重要視されています。大学体育がこの課題に応える方法は、各大学によって異なるかもしれません。大体連もその正解を定めることはできないでしょう。しかし、細分化された専門的な知を再び統合してVUCA時代を乗り越える能力の育成において、大学体育の多様性は多くの参考事例となり、また、Well-beingの獲得の視点からも必ずや共通項が見いだされると考えます。そして、大学体育のネットワークは大学改革、社会変革における「知恵袋」となり、社会に貢献できると考えています。
以上の様に、大体連は現場の教員の皆様の研修・研究活動によって支えられております。また同時に、大学体育教員の養成、次世代の人材育成も重要な使命となります。体育による人間教育を考え、スポーツ振興を考え、Well-beingの獲得を目指すという共通理念を共有するネットワークに仲間を繋ぎ、持続・循環させていく活動が必要と考えます。そのために、是非多くの皆様に大体連の活動に参加いただき、相互に交流していただくとともに、大体連に対して忌憚のないご意見や新たなアイディアを頂戴したいと思います。何卒、ご指導・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。