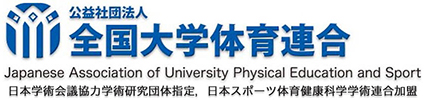文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会の審議において、「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定める科目の廃止を含めた検討がなされています。
公益社団法人全国大学体育連合(大体連)理事会は、同施行規則66条の6が定める科目の一つである「体育2単位」を現状同様に教育職員免許取得の必修科目として維持することを強く求めます。
教育基本法第一章第二条に掲げられている「教育の目標」の第一には、「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと」と明記されています。これは、知・徳・体の調和ある人間形成を目指す日本の教育の基本理念を示すものであり、教員自身がその体現者であることは極めて重要です。
今回の教育職員免許法施行規則第66条の6の見直しは、深刻化する教員不足への対応として、社会人の教職参入を促進しようとするものです。この方向性自体は、教育の多様性や開かれた制度設計の観点から理解できるものです。しかしその一方で、教員養成の過程における「人間教育の根幹をなす身体教育=体育」が形骸化・軽視されるような制度改正が進めば、教育基本法の理念からの逸脱を招きかねません。
教職は知識や技能のみで担える職務ではありません。とりわけ、学校現場では身体を通じた関わりや非言語的なコミュニケーション、他者との協働が日常的に求められます。大学体育は、そうした関係構築力やセルフマネジメント力、さらには自己理解や他者理解を促す教育的経験の場として、極めて本質的な役割を担っています。
さらに、コロナ禍によって身体的なつながりが制限された経験から、教育界は「身体性に根ざした学び」の重要性を改めて認識しています。世界の教育現場では、リアルな体験を通じて「身体知」や「暗黙知」を獲得し、人間関係を構築する力を育むことが、教育の重要な柱として再評価されています。
このような観点からすれば、教員養成課程における「体育」の位置づけを後退させるような制度設計は、教員として求められる人間的成熟や教育的力量を損なうものであり、教育の質の確保という本来の目的にも逆行するおそれがあります。多様な人材の参入を進めるのであればなおのこと、基礎的な身体教育の意義を再確認し、すべての教員志望者が「知・徳・体」のバランスある教育者として育つ環境を確保することが求められます。
以上より、「体育2単位」を削減することにより、対人関係を基本とする専門職である教員の資質形成や教育の質保証に負の影響を及ぼすことが強く危惧されます。大体連理事会は、「教育職員免許法施行規則第66の6」における「体育」科目の位置付けを現状通り維持する方向で慎重な審議・検討がなされることを要望します。
令和7年7月24日
公益社団法人全国大学体育連合理事会
「教育職員免許法施行規則第66条の6」の見直しに関する全国大学体育連合理事会声明